「金属の歴史」4

「鉄はどこから日本へ伝わったのか」
紀元前400年、日本は弥生時代に鉄器文化が始まったとされていますが、これは中国鉄器文化の
直輸入という形で出発したという記録が残っています。今の九州地方が中国と直結していたのに対し、
近畿圏では朝鮮半島と結びついていた可能性が高く、丹後半島(京都府北部)周辺に鉄の輸入窓口が
あったようです。紀元前200年頃になると西日本では広範囲にわたって鉄製品が出土しており、
九州圏では実に70%近くが鉄製の武器に対し、近畿圏での武器の出土はほとんど無かったようです。
九州圏が戦乱であって、近畿圏は平和であったのかどうかははっきりとしておらず、その歴史には
邪馬台国(やまたいこく)が関係したと思われます。
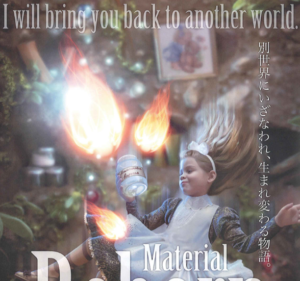
「邪馬台国は九州か近畿か?」
邪馬台国(やまたいこく)は2~3世紀に日本列島に存在したとされる国で、卑弥呼(ひみこ)が治める女王国
であったとして知られていますが、
日本の史書には現れていません。邪馬台国が九州か近畿かで論争が始まったのは江戸時代後期とされ、
21世紀になった今でも歴史学者の説は別れています。
それから200年後の5世紀頃、伽耶地方からの技術をもって日本の本格的な鉄生産が始まったとされています。
日本における製鉄は次の3段階を経て成立したと考えられています。
1)アジア諸国から鉄製品が持ち込まれ、製品を使用する知識をつむ段階
2)あらがねや古くなった製品を材料として新しい鉄製品をつくる段階
3)国内の資源(鉄鉱石や砂鉄)を用いて製鉄が始まった段階
日本は世界に比べ、数百年の遅れで鉄をつくる国となったようです。鉄をつくるために必要な熱処理の技術も
同じく後発であることがわかります。しかし、それから現代に至るまで、鉄の精錬技術は世界最高峰と言われる
までなったのはなぜでしょうか。
それは海に囲まれた日本という国に繋がりがあるのかもしれません。
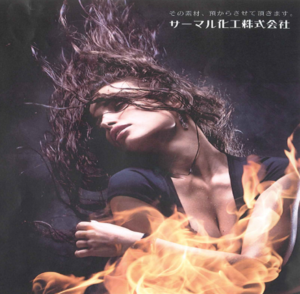
「鉄は東北地方からも入ってきたのか?」
古代東北地方は、いわゆる「化外の地」といわれていましたが、西暦700年頃の大和朝廷の記録に
「東辺北辺の鉄冶置くこと得じ」とあり、みちのくは鉄の鍛冶・加工の先進地域であったと言われています。
幕末には釜石(岩手県釜石市)から洋式高炉に鉄鉱石の精錬が行われたのは、
源流をたどれば製鉄文化の土壌があったからだと考えられます。
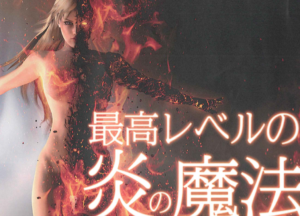
「日本刀の強靭化の方法」
日本刀はたたら法で製鉄されたはるかに不純物の少ない鋼でつくられていた以外に、
強靭化のプロセスがありました。
造り込みおける高炭素材料と、低炭素材料の組み合わせ(甲伏せ造込)で鍛錬されています。
外は高炭素(硬い鋼)内は低炭素(軟かい鋼)を合わせてあり、しなやかさを実現させています。
また、焼き入れ技術により刃はマルテンサイト組織、みねはフェライト組織となっており、
その硬度差は約3倍近くあります。これにより、西洋の剣とは違う、折れにくい日本刀の強靭化が可能と
なっています。
現在の分析技術が無い時代に、永年の技術と経験で磨かれた刀鍛冶の技術で名刀と呼ばれ歴史に名を刻むには
相当の努力があったことは現在の熱処理業として学ぶべき点は多くあるものと感じます。
次回「金属の歴史」5に続きます。
参考文献:株式会社 上島熱処理工業所
顧問 鶴見州宏様
「あらゆる焼鈍ニーズに応える、熱処理・水素還元の専門技術情報サイト」
【熱処理・水素還元技術ナビ】
Produced by サーマル化工株式会社
ぜひご覧ください。
よろしくお願いいたします。
「焼鈍」専用ページはこちらから

「熱処理無料相談窓口を開設いたしました」
「こちらをクリック」していただくと、専用ページに移行します。どんな内容でも構いません。
すべての熱処理に対する疑問、質問、すべてお答えいたします。
熱処理についての解説はブログ欄から「こちらをクリック」してご覧ください。
